もくじ
東京メトロ定期券の解約(払い戻し)全体像
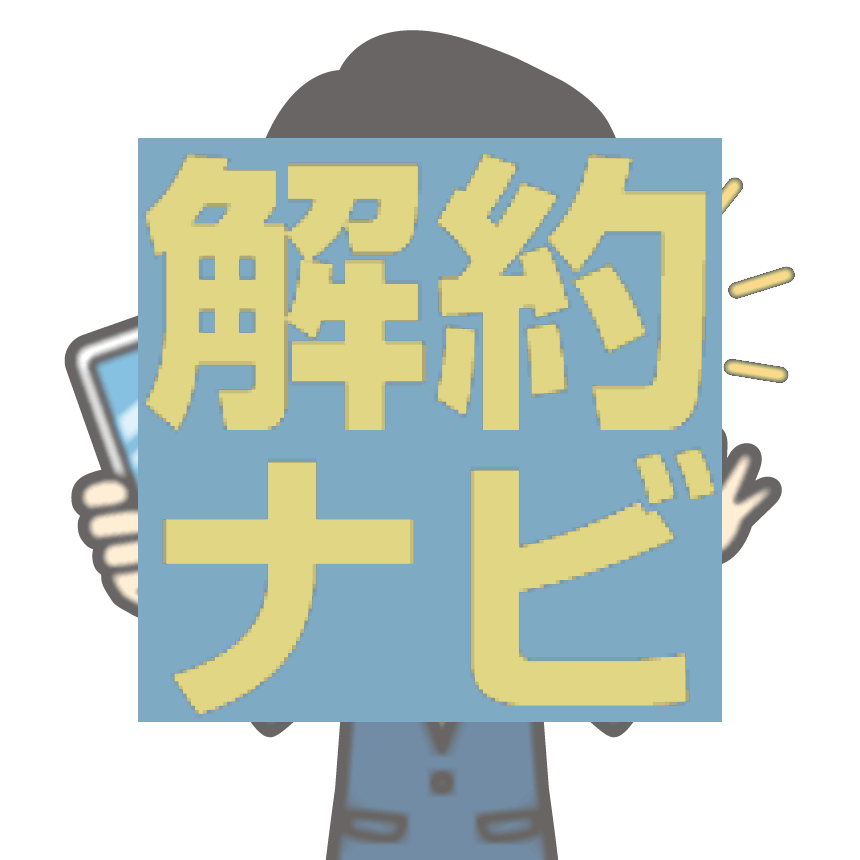
① 東京メトロの定期券種別と発行主体(PASMO/磁気/連絡定期/モバイルSuica)
①-1 発行主体と手続き先の早見表(発行事業者=東京メトロ/他社/連絡定期)
下表で券面・アプリ上の見分け方と、どこで手続きすべきかを一気に確認できるようにまとめました。
| 定期券の種類 | 見分け方(券面・アプリ) | 主な発行主体 | 解約(払戻)手続き先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PASMO定期(カード) | 券面に「発売社名」表記/カード裏面の事業者コード | 東京メトロ or 他社私鉄・バス | 発売した事業者の定期券うりば | 東京メトロ発行であればメトロの定期券うりばへ |
| PASMO一体型(定期+クレカ等) | 一体型券面(提携カード) | 提携発行元(例:カード会社+鉄道事業者) | 券面に記載の発売事業者窓口 | 返金は購入時の支払方法に準じる |
| 磁気定期券 | オレンジ系磁気券/発売社名印字 | 東京メトロ or 他社 | 発売した事業者の定期券うりば | IC化前に発売した旧券も同様 |
| 連絡定期(メトロ+他社) | 券面に複数社の区間表示 | 発売した一方の事業者 | 発売事業者のみ(他社では不可) | 手数料は「定期券ごと」に発生 |
| モバイルSuica定期 | アプリの定期情報(経路に東京メトロを含む) | JR東日本(モバイルSuica) | アプリで払戻/区間変更 | 操作完了と同時に旧定期は即時無効 |
- ポイント:「どの駅で買ったか」ではなく、誰が発売したか(発行主体)で手続き先が決まります。
- 連絡定期は発売主体の窓口一択。誤って相手社に行っても処理できないので注意。
- モバイルSuicaは駅窓口不要(原則)。アプリ内で完結するが、操作タイミングに注意が必要。
①-2 連絡定期の手数料と扱い(「定期券ごと」に発生)
連絡定期の払戻では、手数料は連絡1枚=1件分として扱われます(複数枚に分かれていれば枚数分)。
また、区間の一部だけ解約や片側のみの変更は基本不可で、新規に買い直しとなるケースが多いので気をつけましょう。
- 窓口は必ず発売事業者側(相手社では処理不可)。
- 他社線への乗り入れ事情により、証明書類や処理手順が異なる場合がある。
- クレジット購入の返金は、購入元(カード会社経由)で処理されるのが原則。
② 払い戻し金額の計算ルール
②-1 開始7日以内の計算(往復普通運賃×日数)と具体例(1/3/6か月)
定期の使用開始日から7日以内に解約する場合、払戻額は次の式が基本である。
払戻額 = 定期の発売額 −(往復の普通運賃 × 利用日数) − 手数料220円
例:通勤定期(1か月/3か月/6か月)のイメージ計算(数値は例。実運賃は要確認)。
| 購入期間 | 発売額(例) | 往復普通運賃(例) | 利用日数 | 手数料 | 払戻額の考え方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 10,000円 | 400円 | 5日 | 220円 | 10,000 − (400×5) − 220 = 7,780円 |
| 3か月 | 28,500円 | 400円 | 6日 | 220円 | 28,500 − (400×6) − 220 = 25,880円 |
| 6か月 | 54,000円 | 400円 | 2日 | 220円 | 54,000 − (400×2) − 220 = 53,380円 |
- 「利用日数」は実際に使った日数(改札通過が基準)。
- 学割・区間・運賃改定等により金額は変わるため、最終額は窓口計算が確定。
②-2 7日超〜各月境の「月単位」計算の具体例と“損しないタイミング”表
使用開始から8日目以降は、次の式が原則となっています。
払戻額 = 定期の発売額 −(使用済み月数分の定期運賃) − 手数料220円
ここでいう「使用済み月数」は、1か月単位で切り上げられます(例:1か月券を20日使った=1か月使用)。
損しにくい解約タイミングの目安(例)
| 購入期間 | この日までに解約すれば | 使用済み月数の扱い | ひとこと目安 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 開始7日以内 | 日割り換算 | 早期解約が有利 |
| 3か月 | 1か月満了前 | 1か月分で確定 | 月末直前で判断 |
| 6か月 | 2か月満了前 | 2か月分で確定 | 月境目を意識 |
- 月単位計算では、月境(満了日)直前の解約が比較的有利になりやすい。
- 購入期間が長いほど、初月内に判断できると払戻額が大きく残りやすい。
- 実際は区間・運賃設定で前後するため、駅窓口で試算するのが確実。
③ 必要書類と本人確認・代理人手続き
③-1 本人確認書類・クレジット購入時の返金経路(カード会社経由)
- 必須持参物(本人手続き)
- 定期券本体(PASMOカード/磁気券/モバイルSuicaはアプリ)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・学生証など)
- 購入時のクレジットカード(クレジット購入の場合)
- 領収書・利用明細(あればスムーズ)
- 返金経路
- 現金購入:窓口で現金返金(または指定方法)。
- クレジット購入:原則、購入に使用したカードへ払戻(カード会社経由)。
- キャッシュレス(交通系IC・コード等):原則、購入元の決済手段に準じる(要確認)。
注意:カードをすでに解約・再発行している場合は、カード会社側の案内に従う(一時的口座振込等の代替手続きになることがある/要確認)。
③-2 代理人の委任状・公的証明の要件(要原本・写し)
- 代理人でできること:本人の委任状と必要書類が揃っていれば、定期の払戻は手続き可能。
- 必要書類(代表例)
- 委任状(本人自署・押印が望ましい)
- 本人確認書類の原本または写し(駅の案内に従う)
- 代理人の本人確認書類(原本)
- 定期券本体
- 購入時のクレジットカード(クレジット購入時)
- NGになりやすいケース
- 委任状の記載不備(日付・氏名・対象定期の特定欄の抜け)
- 本人確認書類の有効期限切れ
- クレジット購入で名義が本人と異なる(名義人本人の来場が必要になる場合あり)
補足:書類要件や取り扱いは駅・事業者で運用差があるため、不明点は事前に問い合わせると確実です(要確認)。
経路別ステップ|東京メトロ定期券の解約(うりば/営業時間外/駅)
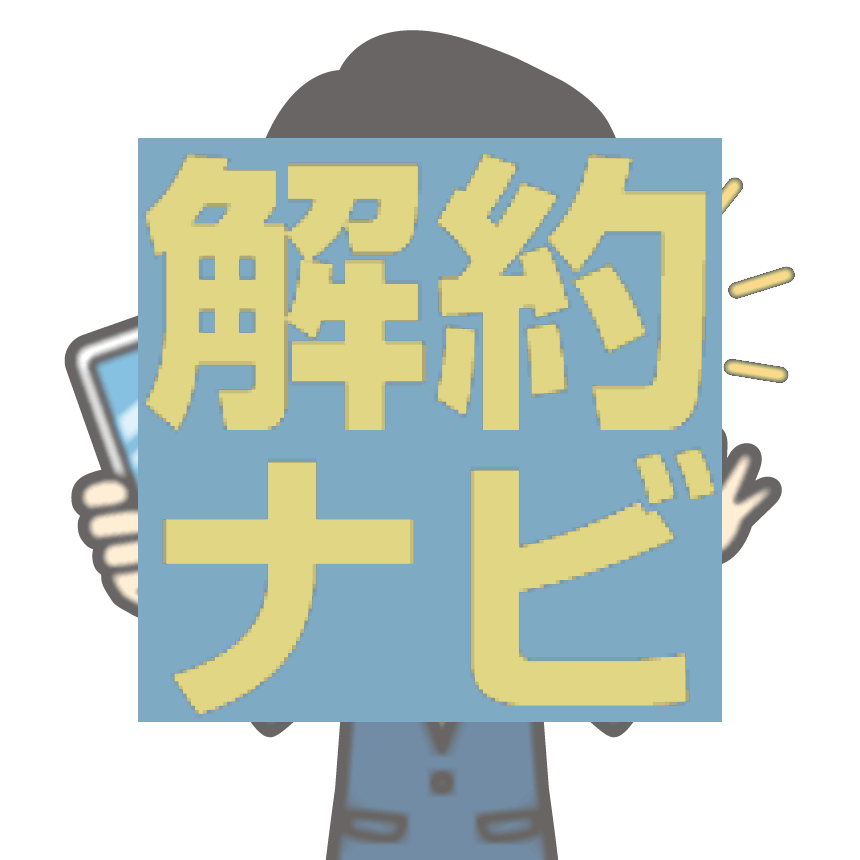
① 定期券うりばでの払い戻し手順(当日完結)
①-1 うりば所在一覧と最寄の探し方(路線別リスト)
東京メトロの定期券うりばは主要駅に設置されています。以下は路線別の一例です(最新情報は公式サイト要確認)。
| 路線 | 設置駅(例) |
|---|---|
| 銀座線 | 浅草、上野、銀座 |
| 丸ノ内線 | 池袋、新宿、荻窪 |
| 東西線 | 中野、西船橋 |
| 日比谷線 | 北千住、築地 |
| 半蔵門線 | 渋谷、大手町 |
| 南北線 | 目黒、赤羽岩淵 |
| 有楽町線 | 和光市、有楽町 |
| 副都心線 | 和光市、渋谷 |
- 営業日・時間は駅ごとに異なるため、事前に東京メトロ公式ページの「定期券うりば案内」を確認。
- 混雑を避けるなら平日午前や昼過ぎが狙い目。
①-2 持ち物チェックリスト(定期券本体/本人確認/購入カード 等)
- 定期券本体(PASMOカード/磁気券/モバイルSuicaはアプリ表示)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・学生証など)
- 購入時のクレジットカード(クレジット購入の場合)
- 領収書・利用明細(任意だがスムーズ)
注意:モバイルSuica定期はアプリから手続きするため、駅窓口には不要(ただし区間変更や確認で訪れる場合あり)。
② 営業時間外→駅で「払戻申出証明」をもらう手順
②-1 申出証明の受け取り〜後日の同日扱い再現フロー図
どうしても定期券うりばの営業時間に間に合わない場合は、最寄りの東京メトロ駅で「払戻申出証明」を発行してもらいます。これにより、後日うりばでの手続きが証明日=解約日として扱われます。
- 駅係員に「定期券の払い戻しをしたいが営業時間外」と伝える
- 定期券本体を提示し、証明書を発行してもらう
- 証明書と定期券を保管(紛失注意)
- 後日うりばに持参して正式な払戻手続き
②-2 申出日からの期限・必要書類(要確認:各駅裁量の運用差がある可能性)
- 申出証明の有効期限は概ね数日〜1週間程度(駅によって異なるため要確認)
- 必要書類は基本的に通常の払戻と同じ(定期券本体、本人確認、支払方法の証明)
- クレジット購入分はカード会社経由返金のため、カード持参必須
注意:運用は駅によって若干異なるため、発行時に有効期限と必要物を必ず確認すること。
③ うりばが遠い場合の来場往復の扱い(運賃精算の注意点)
③-1 うりばまでの乗車→証明→運賃払い戻しの取り扱い(東京メトロの案内)
定期券うりばまでの移動に定期区間外を利用する場合、条件によっては往復運賃が払い戻されることがあります。
- 定期券区間外を含む乗車でうりばに行く
- 解約手続きと同時に係員に運賃精算の旨を申告
- 対象の場合、実費相当分が返金される
ポイント:全てのケースで返金されるわけではなく、「払戻手続きのための来場」である証明が必要になる場合がある。
③-2 都営参考:同様の「証明」運用事例(ベンチマーク)
都営地下鉄では、払戻目的で駅を訪れる際に係員が「来場証明」を発行し、後日運賃返金に充てる事例があります。東京メトロでも同様の運用がある駅がありますが、全駅共通ではないため、事前確認が安心です。
- 事前に電話で該当駅に問い合わせ
- 証明書の有効期限と必要物を確認
PASMO定期(カード/一体型)の解約方法|東京メトロ発行分
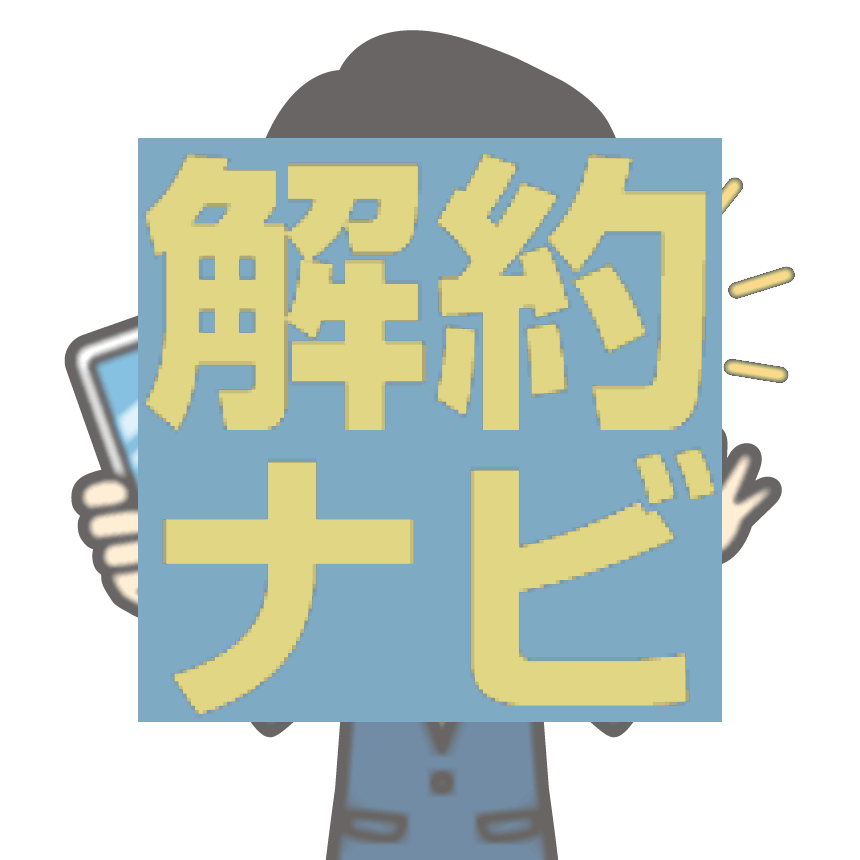
① 東京メトロ発行PASMO定期の手順
①-1 うりばでの流れ・持参物・注意点(クレジット購入時の返金)
- 発行事業者(東京メトロ)の定期券うりばに行く
- 解約(払戻)を希望する旨を伝える
- 必要書類を提示(定期券本体・本人確認書類・購入カードなど)
- 窓口で払戻額を計算→同意後に返金処理
- 持参物チェックリスト
- PASMOカード(定期券情報が記録されたもの)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、学生証など)
- 購入時に使用したクレジットカード(クレジット購入の場合)
- 領収書や利用明細(任意だが手続きがスムーズ)
- クレジット購入分の返金はカード会社経由になるため、現金での受け取りはできません。
- 購入カードをすでに解約している場合は、カード会社に事前確認を行っておくと安心です。
①-2 連絡定期(メトロ+他社)の注意点と問い合わせ先リンク集(PASMO一覧)
連絡定期の場合でも発行事業者の窓口でしか手続きできません。他社区間を含む場合でも、発売主体が東京メトロであればメトロの窓口へ行きます。
- 券面に記載されている発売事業者を確認(例:「発売社:東京メトロ」)
- PASMO公式サイトには各発行事業者の問い合わせ先一覧があります
② 他社発行PASMO定期を東京メトロ駅で解約したい場合
②-1 原則不可→発行事業者へ(判断ポイントと券面の見方)
他社が発行したPASMO定期は、東京メトロの駅やうりばでは解約できません。発行事業者を確認し、その会社の定期券うりばに行ってください。
- 判断ポイント
- 券面の「発売社」欄
- カード裏面の事業者コード
- JR東日本発行の「Suica定期」や、他私鉄発行のPASMO定期も同様に発行元でのみ解約可能です。
②-2 よくある勘違いと解決策(乗換駅で誤って並ばないコツ)
- 連絡定期=どちらの会社でも解約できる、と思い込むケースがありますが誤りです。
- 乗換駅で両社の窓口がある場合、必ず自分の定期を発行した側に並ぶこと。
- 迷った場合は改札係員に券面を見せて「発行元はどこか」確認しましょう。
モバイルSuica定期の解約・区間変更(東京メトロを含む場合)
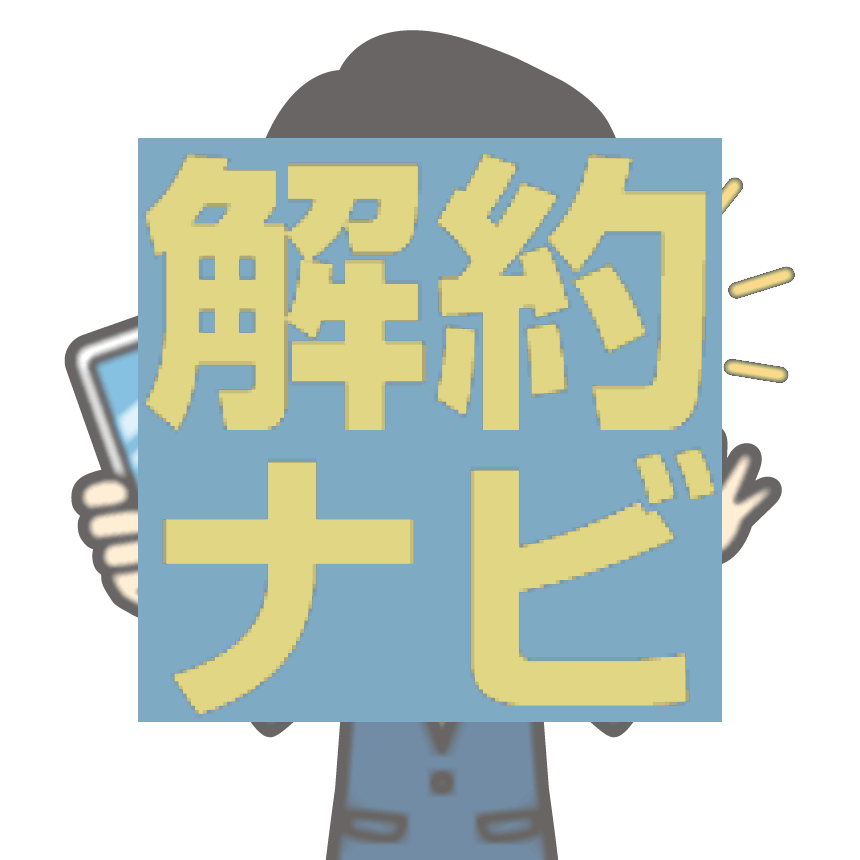
① 払い戻しの基本(アプリ操作と返金経路)
①-1 払戻し操作の流れ(履歴確認は会員サイトのみ)
- モバイルSuicaアプリを開き、「チケット購入・Suica管理」メニューから定期券を選択
- 「払戻し」または「定期券の解約」を選ぶ
- 内容と払戻額を確認し、実行
- 処理が完了すると、その時点で定期券情報が削除され、即時利用不可になる
- 払戻しの履歴はアプリ内ではなく、モバイルSuica会員サイトにログインして確認可能
- 操作は通信環境の良い場所で行う
- 処理後は改札を通れなくなるため、必ず下車後に実行する
①-2 クレジット返金タイミングと注意点(要確認:カード会社処理日)
- モバイルSuicaの払戻しは購入時に使用したクレジットカード経由で返金される
- 返金反映までの期間はカード会社によって異なり、数日〜翌月請求明細での相殺となることもある
- カードをすでに解約・再発行している場合は、カード会社に直接問い合わせて受け取り方法を確認する
② 区間・経路変更時の落とし穴
②-1 変更=旧定期自動払戻し→即時利用停止のリスクと実例対策(実行は下車後に)
モバイルSuicaで区間変更を行うと、旧定期は自動的に払戻し処理され、即時に利用できなくなります。
- 通勤途中に変更を実行すると、帰りに旧定期が使えず運賃を別途払うことになる
- 対策:必ず下車後、帰宅後など利用予定がない時間に変更を実行する
- 翌日以降の利用に備えて、新しい定期の有効開始日も事前に確認する
②-2 返金ゼロになりやすいケース(残余期間が少ない場合)と判断基準
- 有効期限が残りわずか(例:数日〜1週間)の場合、払戻額は手数料で相殺されて返金ゼロになることがある
- 計算は「(発売額 − 使用済み期間分の定期運賃) − 手数料220円」が基本
- 判断基準:残り日数と定期区間の往復運賃を照らし合わせ、払戻額がプラスになるかを事前に試算する
学割(通学定期)・証明書の確認とWeb予約の制約
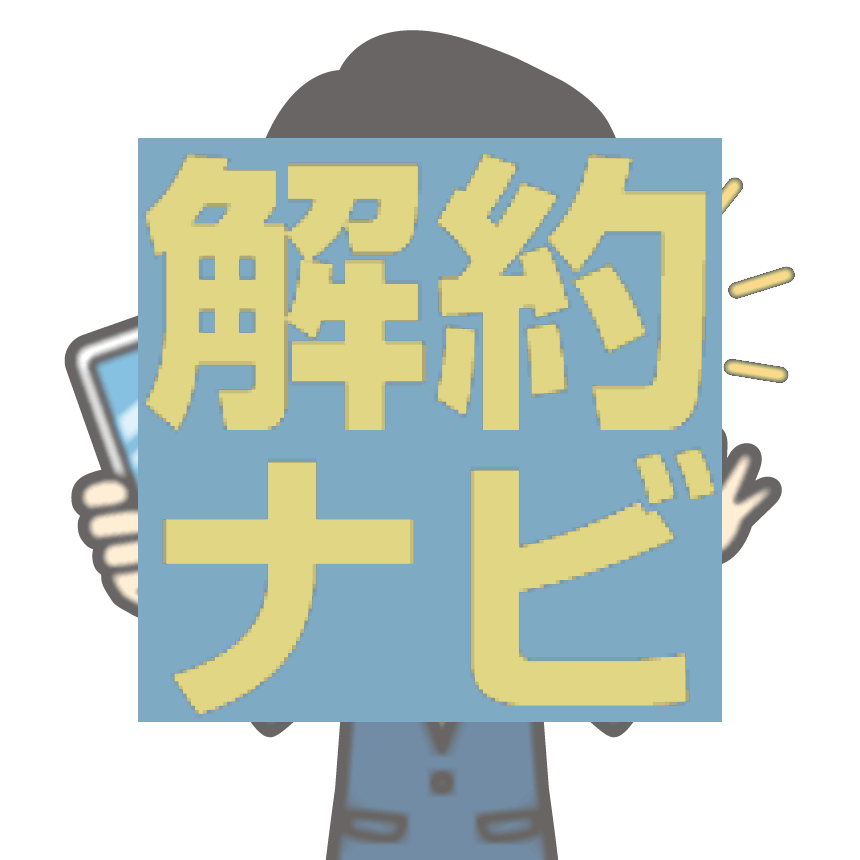
① 東京メトロ通学定期の購入・確認フロー
①-1 駅係員による証明書確認→ピンクの多機能券売機で購入
- 学校が発行した通学証明書(または通学定期券購入兼用証明書)を準備
- 東京メトロの駅窓口で駅係員による書類確認を受ける
- 証明書が有効と確認されたら、ピンク色の多機能券売機で通学定期を購入
- 証明書は有効期間内であることが条件
- 初めての購入や学校・区間変更時は必ず書類確認が必要
①-2 12歳→4/1有効分の事前予約制限(予約不可の注意)
- 小学校から中学校へ進学するなど、12歳から新学年の4月1日有効分の定期はWeb予約不可
- この場合は直接駅窓口で書類確認のうえ発行手続きが必要
- 予約不可条件は年齢だけでなく、証明書の種類や有効開始日にも依存するため要注意
② 都営の通学定期の参考条件(比較用)
②-1 購入可能媒体と認定学校の範囲(参考)
都営交通の通学定期は、PASMO・Suicaのどちらでも発行可能で、対象は認定校に限られます。
- 認定校は都営交通の公式サイトで確認可能
- 東京メトロと異なり、購入手続き場所や証明書提出方法に差があるため、乗り継ぎ利用時は両方の条件を確認する必要あり
③ 学期途中の解約は得か損か
③-1 6か月購入→途中払戻しの“損”パターン
6か月定期を学期途中で解約すると、使用済み期間を月単位で計算するため、残り期間が少ないと払戻額がほとんど残らない場合があります。
- 例:6か月定期を3か月半で解約 → 4か月分として計算される
- 残額が手数料(220円)で相殺されるケースもある
- 進学や転居で途中解約の可能性がある場合は、短期(1〜3か月)購入の方が損失を抑えられる
ケース別トラブル対処(よくある失敗と回避策)
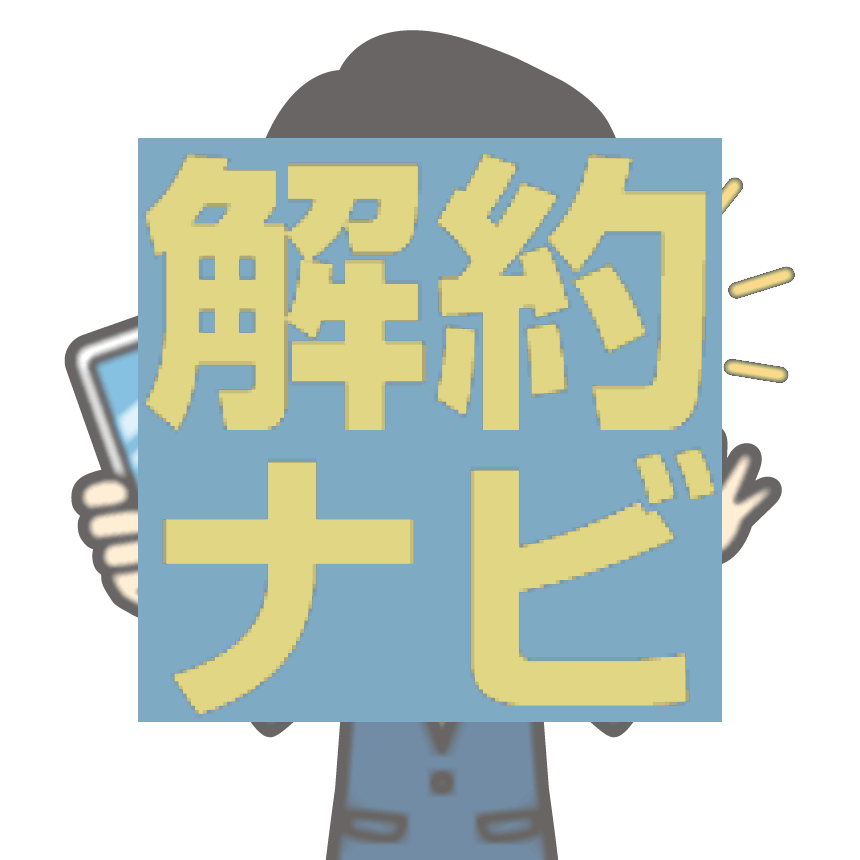
① 連絡定期の手数料・窓口判断ミス
「定期券ごと」手数料の数え方と窓口の見極め方
- 連絡定期は1枚ごとに手数料が発生します。例えばメトロ+JR連絡定期と別途バス定期を持っている場合、それぞれに手数料がかかります。
- 窓口は発行事業者のみが対応可能です。他社窓口では解約不可。
- 判断方法:券面に記載された「発売社」欄やカード裏面の事業者コードを確認。
回避策:解約前に発行元を確認し、訪問先を間違えないようにしましょう。
② クレジットカードを解約してしまった
原則カード会社への払戻し→対処フロー(要確認:カード会社ごとの運用差)
- クレジット購入した定期券の払戻金は購入時のカードに返金されます。
- カード解約済みの場合も、契約していたカード会社が返金処理を行い、指定口座への振込などで対応することがあります。
- カード会社によって運用が異なるため、事前に問い合わせて返金方法を確認しましょう。
回避策:解約予定がある場合は、定期の払い戻しを先に済ませてからカード解約を行うとスムーズです。
③ 本人が行けない(代理人対応)
委任状・本人確認のセットとNG例
- 代理人手続きには以下が必要です:
- 本人記名の委任状(日付・氏名・対象定期区間を明記)
- 本人の身分証明書(原本または写し)
- 代理人の身分証明書(原本)
- 定期券本体
- クレジット購入の場合は購入カード
- NG例:
- 委任状の記載漏れ(氏名や日付抜け)
- 身分証の有効期限切れ
- クレジット名義が本人と異なる場合(名義人本人来場が必要になることあり)
回避策:駅や公式サイトで委任状フォーマットを事前に確認し、不備のない状態で持参しましょう。
④ 営業時間に間に合わない
駅での「払戻申出証明」→後日うりばで同日扱い実現手順
- 営業時間外に駅係員へ「定期券払戻希望だが、うりばが閉まっている」と伝える
- 定期券本体を提示し、「払戻申出証明」を発行してもらう
- 証明書と定期券を保管(紛失に注意)
- 有効期限内にうりばへ持参すると証明発行日扱いで払戻が可能
回避策:有効期限や必要物を証明書発行時に確認し、早めに手続きを完了させましょう。
乗り換え検討(都営・JR・私鉄の参考情報)
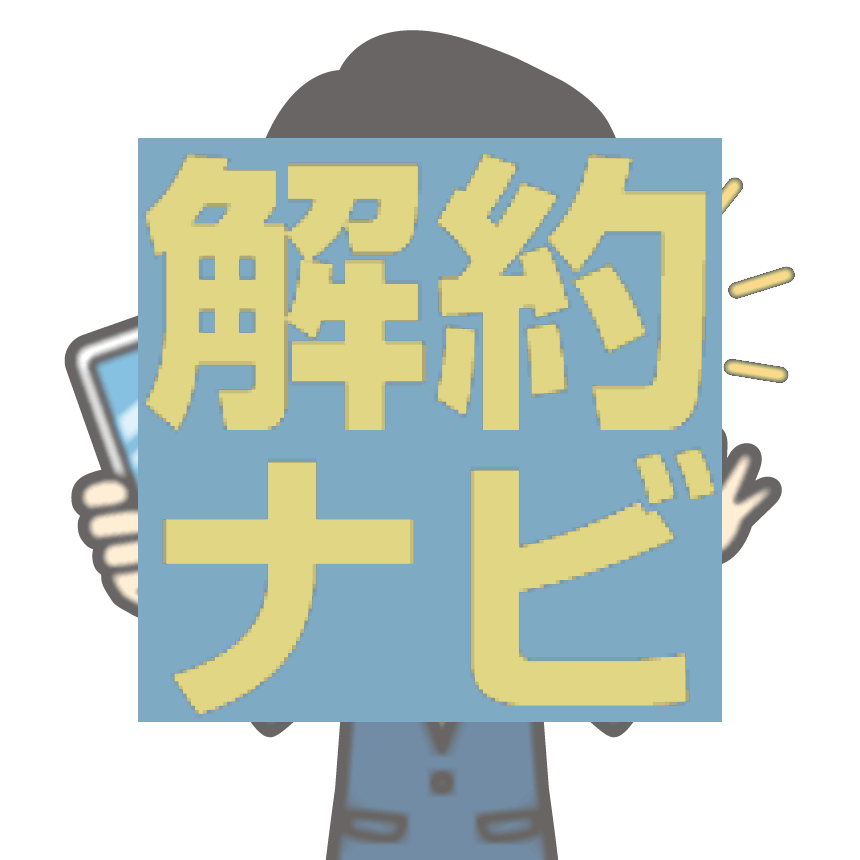
① 旧→新の切替タイミング最適化
「開始7日以内」や月末・月初の損益分岐を意識(早見表)
定期券は開始7日以内なら日割り計算、それ以降は月単位計算が適用されます。新定期への切り替え時は、このルールを踏まえて損しない日を選びましょう。
| 旧定期の利用期間 | 払戻計算方式 | 切替推奨タイミング | 理由 |
|---|---|---|---|
| 開始から7日以内 | 日割り | できるだけ早く | 利用日数分だけ差し引かれるため損失が少ない |
| 8日〜月末前 | 月単位 | 月末直前または月初 | 月単位切り上げなので中途半端な日に切替えると損になる |
| 長期定期(3か月・6か月) | 月単位 | 月境の直前 | 未使用月分が多く残るタイミングでの解約が有利 |
- 切替前に旧定期の払戻額を駅で試算してもらうと安心です。
- 新定期の開始日は旧定期の有効期限や解約日を踏まえて設定しましょう。
② 他社線を含む連絡定期からの移行
発行主体の確認と問い合わせ先への動線(PASMO事業者一覧)
連絡定期を解約して別会社の定期に切り替える場合、発行主体の窓口でしか払戻手続きはできません。
- 券面の「発売社」欄またはカード裏面の事業者コードで発行主体を確認
- 発行主体が東京メトロの場合はメトロの定期券うりばへ
- 発行主体が他社の場合は、その会社の窓口や定期券うりばへ
PASMO事業者一覧(公式サイト)を活用して、該当事業者の連絡先や窓口所在地を事前に調べておくとスムーズです。
FAQ(東京メトロ 定期 解約・変更の疑問)
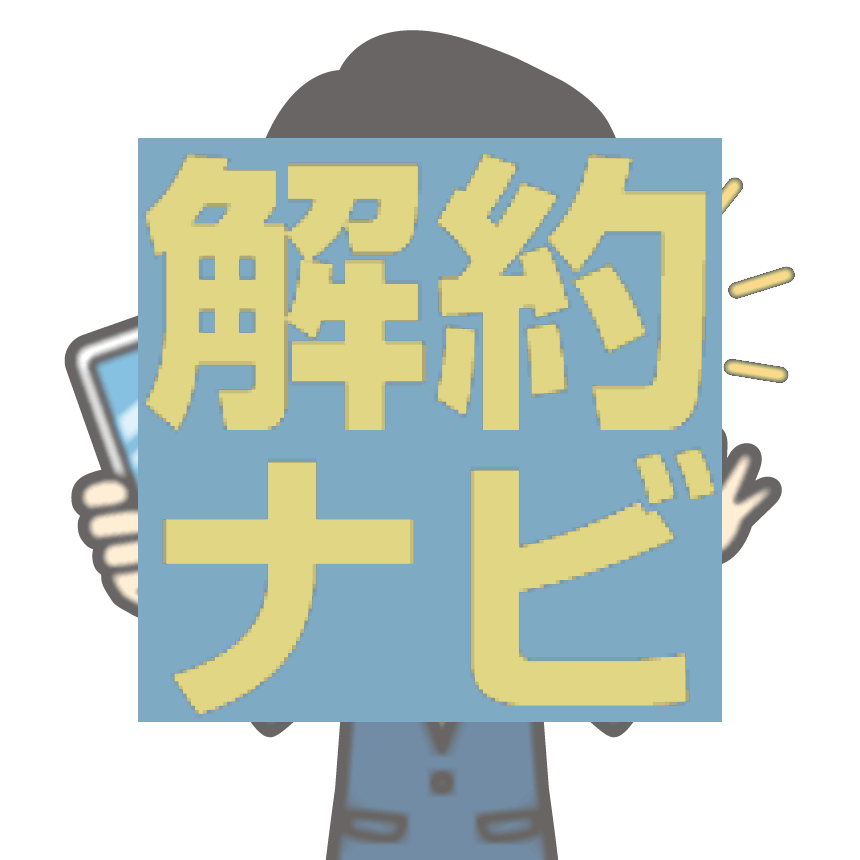
① 「どこで解約できますか?」
発行事業者の定期券うりばが原則/他社発行は不可
- 解約(払戻し)は発行事業者の定期券うりばでのみ可能です。
- 東京メトロ発行の場合は東京メトロの定期券うりばへ。
- 他社発行(JR・他私鉄など)は、その会社の窓口でのみ解約可能です。
② 「返金はいくらですか?」
7日以内の日割り/以後は月単位+手数料220円
- 使用開始日から7日以内:日割り計算(往復普通運賃×利用日数)− 手数料220円。
- 8日以降:月単位計算(使用済み月数分の定期運賃)+手数料220円。
- 残り日数や区間によっては返金がゼロになることもあるため、事前試算がおすすめです。
③ 「代理で手続きできますか?」
委任状+身分証で可。クレジット購入は名義人要。
- 代理人による手続きは委任状と本人確認書類の提示で可能です。
- 代理人自身の身分証明書も必要です。
- クレジットカード購入の場合はカード名義人本人が手続きするのが原則です。
④ 「営業時間外はどうすれば?」
駅で申出証明→後日うりばで同日扱い
- 定期券うりばが閉まっている場合は、最寄駅で「払戻申出証明」を発行してもらいます。
- この証明を後日うりばに持参すれば、発行日と同日扱いで払戻しが可能です。
- 証明書の有効期限は駅で確認してください。
⑤ 「モバイルSuicaで区間変更すると?」
変更確定で旧定期は即使用不可(下車後に実行)
- モバイルSuicaで区間変更を行うと、旧定期はその瞬間から使えなくなります。
- 通勤・通学中に操作すると、帰りに旧定期が使えず運賃を別途払うことになるため注意が必要です。
- 必ず下車後など利用予定がない時間に実行しましょう。
【まとめ】【解約方法】東京メトロの定期券払い戻し・変更 完全ガイド
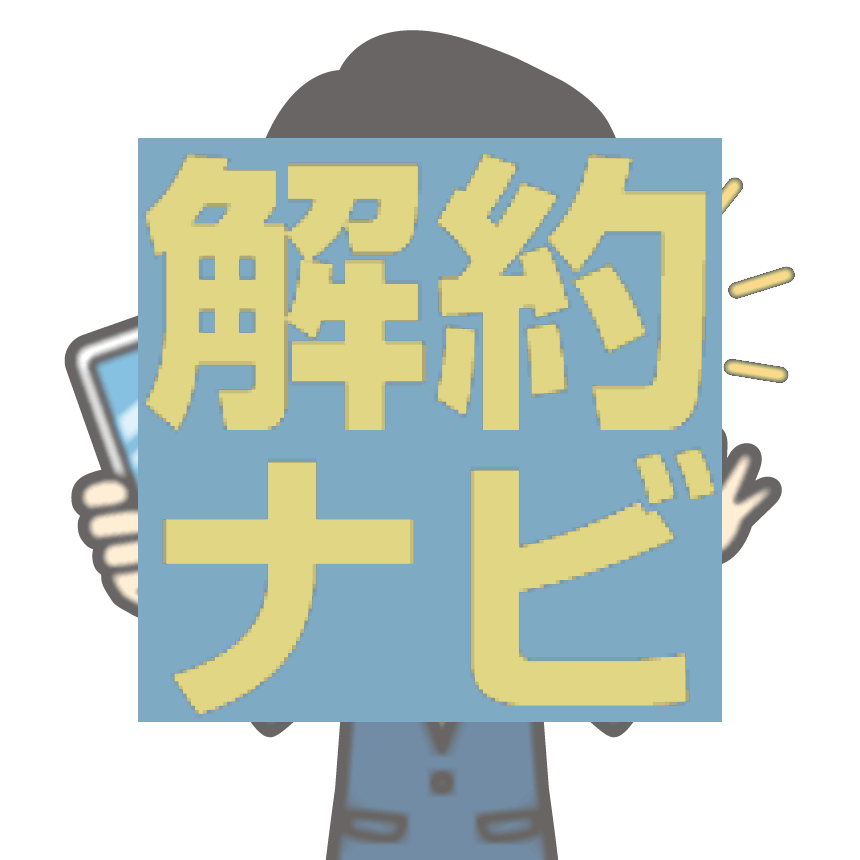
- 払戻しは「開始7日以内=日割り」/以降は月単位+手数料220円。
- 営業時間外は駅で「払戻申出証明」→後日うりばで同日扱い。
- 連絡定期は「定期券ごと」に手数料、発行主体で窓口が決まる。
- モバイルSuicaの区間変更は旧定期が即時無効化、下車後に実行。
- 学割は証明書確認必須・Web予約や媒体に制約あり。
